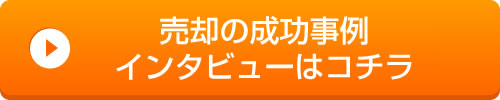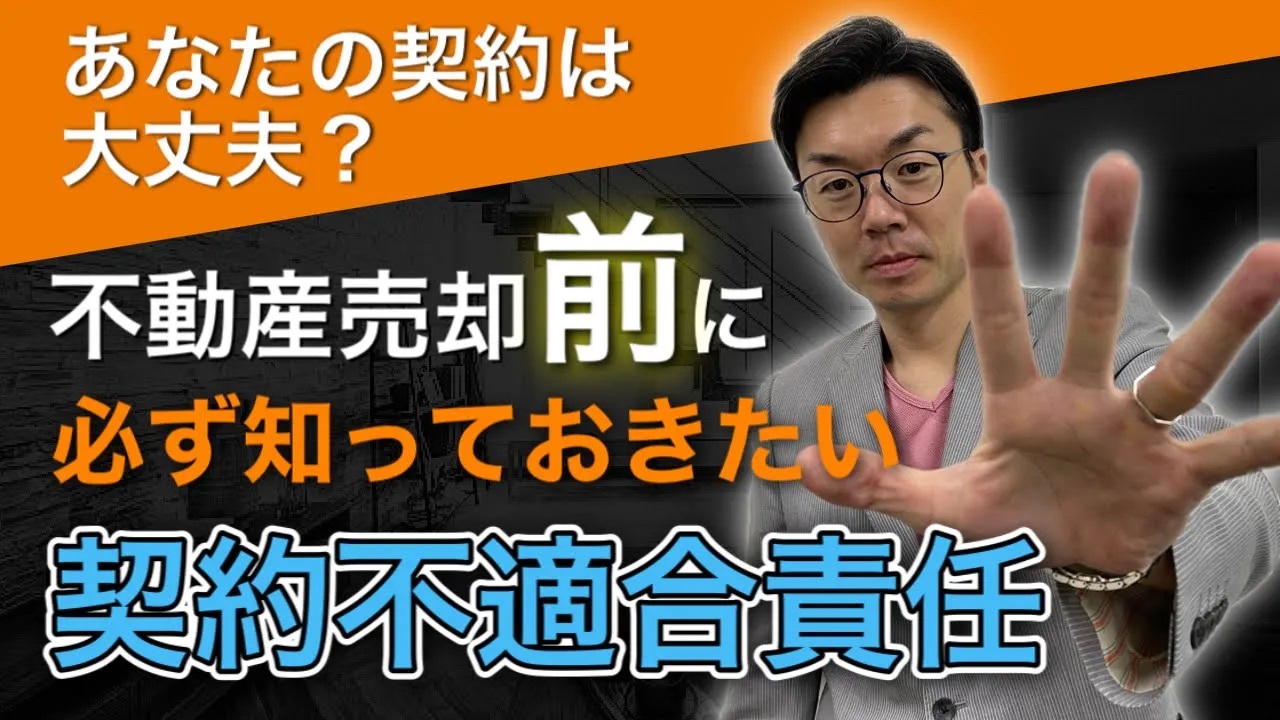【不動産売却】見逃しがちな「ブロック塀」に注意!トラブルになる越境・共有・高さ違反の解決策

不動産を売却する際、建物の内装や設備の不具合を気にされる売主様は多いですが、実はもっと深刻なトラブルになりやすい場所があります。
それは、隣地との境界にある「ブロック塀」です。
「古い塀だけど、今まで問題なかったから大丈夫だろう」 そう思って売却をスタートすると、契約直前になって「塀が建築基準法に違反していました」「塀の是正が必要です」「買主の住宅ローンが通りません」と言われてしまうケースが多くあります。
今回は、不動産売却におけるブロック塀の3大トラブル、
- 越境(えっきょう)
- 共有(きょうゆう)
- 高さ制限違反(1.2mルール)
について、それぞれの解決策を分かりやすく解説します。
塀が隣地に「越境」している場合
「越境」とは、こちらの塀の一部(または基礎部分)が隣の敷地にはみ出している状態、またはその逆の状態を指します。
昔の測量は現在ほど精密ではなかったため、築年数が経過した物件では「数センチの越境」は珍しくありません。また、長年の重みで塀が傾き、空中で越境しているケースもあります。
売却時のリスク
越境がある状態を調査・告知しないで売却を進めると、購入した買主様が将来隣地と揉める原因になります。そのため、買主様からは不動産を引き渡すまでに「越境を解消してから引き渡してほしい」と求められることが一般的です。
解決策:覚書(おぼえがき)を結ぶ
今すぐに塀を壊して作り直すのは費用もかかり大変です。そこで、隣地の方と「越境の覚書」を取り交わします。
覚書の内容
「現在は越境している事実をお互いに確認しました。今の塀があるうちはそのままで良いですが、将来、建て替えや作り直しをする際には、正しい境界線内に収めます」という約束を書面化します。
この書面があれば、買主様も安心して購入することができます。
塀が隣地と「共有」である場合
境界線の上に塀が立っており、お互いの費用で設置した、あるいはお互いの所有物として認識しているケースです。
売却時のリスク
共有の塀は、民法上「共有者の同意」がないと、変更や取り壊しができません。買主様が「自分の好きなフェンスに変えたい」と思っても、お隣の承諾が得られなければ何もできないのです。また、将来の補修費用を誰が負担するかで揉める可能性もあります。
解決策:承継(しょうけい)の合意を得る
売却前に、隣地の方と話し合い、以下の点を確認・書面化しておきます。
- 所有権の確認: 誰の持ち物か(共有なのかなど)。
- ルールの引継ぎ: 「売却後は、新しい買主(新所有者)にこの権利と義務を引き継ぎます」という承諾を得ておきます。
これをしておかないと、買主様は「お隣さんがどんな人かわからないし、共有物はリスクが高い」と購入を躊躇してしまいます。
高さが1.2mを超え、建築基準法に違反している場合
これが近年、最も厳しく見られているポイントです。 特に2018年の大阪北部地震以降、古いブロック塀の安全性に対する基準は非常にシビアになりました。
なぜ「1.2m」が基準なのか?
現在の建築基準法では、高さが1.2mを超えるブロック塀には、「控え壁(ひかえかべ)」という支えを3.4mごとに設置する義務があります。
しかし、古いブロック塀の多くは、この「控え壁」がありません。 つまり、「控え壁がないのに高さが1.2mを超えているブロック塀」は、現在の基準に適合しない(違反または既存不適格)危険な塀とみなされます。
売却時のリスク
- 融資否決: 違法状態の工作物がある物件には、銀行が住宅ローンを貸さないケースが増えています。
買主の建物建築に悪影響:基準に適合しない塀が存する状態では、買主が新たに新築する建物の建築許可が得られない可能性があります。 - 契約不適合責任: 安全性を欠いた塀をそのまま引き渡して事故が起きた場合、売主様が責任を問われる可能性があります。
解決策:3つのパターン
- 解体・新設する:最も確実な方法です。危険なブロック塀を解体し、軽量なフェンスなどに作り替えます。費用はかかりますが、物件の印象も良くなり、買主様の不安もなくなります。
- 上段をカットする:ブロック塀の上数段をカットして、高さを1.2m以下にします。これなら控え壁がなくても基準内となり、安全性も高まります。
- 現状有姿で売却(条件付き):どうしても費用をかけられない場合、「塀が基準を満たしていない旨」を重要事項説明書で明確に告知し、買主様の責任で直してもらう条件で売却します。
もし「共有」で「違反(状態)」だったら?
一番難しいのが、「お隣との共有塀で、しかも高さが1.2mを超えている」というケースです。
この場合、ご自身の判断だけでは「高さをカット」したり「解体」したりすることができません。売却活動を始める前に、不動産会社を通じてお隣の方と相談し、「地震が来たらお互いに危ないので、この機会に低くしませんか?」と交渉する必要があります。
【実録】私が現場で経験した「塀」のトラブル事例
ここまで法律やルールの話をしてきましたが、実際の不動産取引の現場では、もっと複雑な事情が絡むことがあります。 私がこれまでに経験し、解決してきた事例を2つご紹介します。
ケース1:共有だと思っていた塀が「越境」しており、即時解体を要求された事例(杉並区)
【状況】 杉並区の住宅街にある戸建て売却の事例です。 隣地との境界線上にはブロック塀がありましたが、高さは1.2m未満で安全性に問題はありませんでした。売主様からは「お隣との共有の塀です」と伺っており、そのまま引き継ぐ予定でした。
【発覚したトラブル】 境界確認のために隣地の所有者様とお会いし、「塀は共有ということでよろしいでしょうか?」と確認したところ、意外な事実が判明しました。 隣地の方いわく、「いいえ、それはそちら(売主様)の単独所有で、しかもこちらの敷地に越境しています」 とのこと。
【解決への道】 通常、越境がある場合は「将来建て替える時に直しましょう」という覚書(おぼえがき)を交わして解決することが多いのですが、この隣地の方は「即時の解体を望む。解体して敷地内に作り直さない限り、境界確認のハンコは押さない」と非常に強い意向を示されました。
境界確認書がないと売却が難航するため、売主様と相談の上、販売前に既存の塀を解体し、売主様の敷地内に新しい塀を再構築しました。 結果として、無事に境界確認書を取得でき、買主様には「新品の塀で、境界トラブルもない状態」として安心して購入していただくことができました。
ケース2:隣の家の塀が危険!交渉して解決した事例(大田区)
【状況】 大田区での土地取引の事例です。 こちらの土地には問題がなかったのですが、北側の隣地に立っているブロック塀が高さ2mもあり、一部破損しているなど倒壊の危険がある状態でした。
【想定されるリスク】 この塀は隣地の方の所有物であり、越境もしていませんでした。しかし、買主様が現地を見れば「隣の塀が崩れてきそうで怖い」と感じるのは必至です。このままでは売却の大きな足かせになります。
【解決への道】 そこで販売活動を開始する前に、私たちが間に入り、隣地の方へ交渉を行いました。 「地震などで倒れるとお互いに危険ですので、この機会にやり替えませんか?」と提案し、費用を折半することで合意。 危険な高い塀を撤去し、高さ3段の安全なブロック塀+目隠しフェンスへと作り替えました。
これにより、隣地の方は費用を抑えて塀を直すことができ、こちらは懸念材料がなくなり、買主様に不安を与えることなくスムーズに売却を成功させることができました。
まとめ:塀の問題は「プロの調査」と「隣地との対話」が鍵
上記の事例のように、ブロック塀の問題は「高さ」や「法律」だけでなく、「隣地の方との関係性」や「交渉」が非常に重要になります。
自己判断で「大丈夫だろう」と進めてしまうと、後から「解体してください」と言われたり、買主様が見つからなかったりと、大きな痛手になりかねません。
ご自宅の売却を検討されたら、まずは私たち不動産会社にご相談ください。 現地を拝見し、
- 境界標はあるか?
- 越境の可能性はあるか?
- 塀の安全性や、隣地との関係はどうなっているか?
これらをプロの目でチェックし、必要な場合は隣地の方との交渉も含めてサポートいたします。
早めの準備で、安心安全な売却を目指しましょう。
この記事を書いた人

- 山﨑 紘靖
- 過去に200件以上の不動産売却に携わり、 某大手不動産会社で営業成績No,1だった山崎が、 売却の専門家として、あなたの「最高額で売れた」をサポートします。
お問合せから第二の人生が始まります。
相談は無料です。ご依頼お待ちしています。
-
- お電話でのお問い合わせ
- 03-6450-7073
-
- FAXでのお問い合わせ
- 03-6450-7138